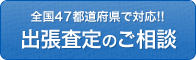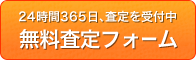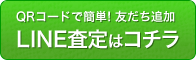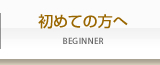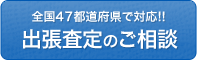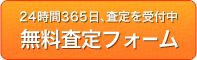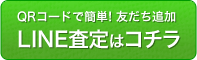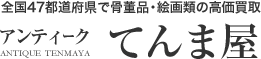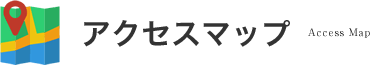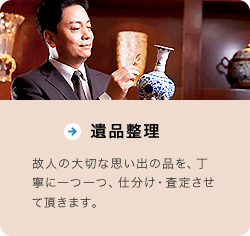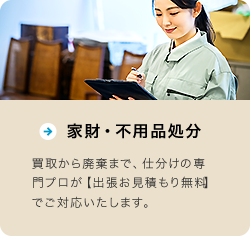作 家三輪休雪
代々長州藩の御用窯をつとめてきた名門の陶家 三輪休雪
三輪休雪とは名跡のひとつで、江戸時代のはじめから萩藩、長州藩で御用窯をつとめてきた三輪窯の当主が継いできた名前です。
現在は十二代目となっており、数ある陶芸一族なかでも特に長い歴史を誇ります。
三輪休雪が得意としているのは萩焼と呼ばれるジャンル。
萩焼においては、砂の多い土をメインに使い、そこに鉄分を多く含んでいるいくつかの種類の土を混ぜ合わせていくことで、ユニークな土としていきます。
釉薬には白く濁るタイプの藁灰釉や透き通った土灰釉などを使います。
焼成の工程においては、比較的高い1000度程度で行われるのが一般的ですが、それほど極端な高温では行われません。
そのため、熱がゆっくりと伝わっていくことになり、手触りのしっとりとした萩焼の独特な触感が生まれると言われています。
時代によって特色の異なる、三輪休雪の焼き物
萩焼の名手として知られる三輪休雪。
現在は十二代目ですが、骨董品マーケットにおいては、先代、先々代、さらに前の当主による作品が取り引きされる機会が少なくありません。
特に、十代目三輪休雪の作品は、古萩焼のエッセンスを巧みに引き出しながら、当時の品格はそのままに面取りを施すことで、モダンで一ひねりのある造形を提案。
焼かれた作品の数も少ないため、モダンな萩焼を探しているコレクターに特に人気の高いラインナップとなっています。
このように、三輪休雪はそれぞれの当主による個性が発揮された作品を数多く輩出。
しかも、それぞれの時代のモードやファッションを上手に取り入れたデザインとなっているものばかりですので、いろいろな好みやテイストによって評価が異なるということが珍しくありません。
これは三輪休雪に限ったことではありませんが、骨董品マーケットではひとつの価値観ですべての取り引きが行われるわけではなく、さまざまな価値観が交錯しながら取り引きが行われている場所でもあるのです。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |