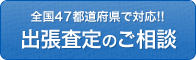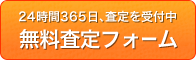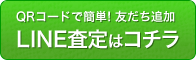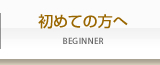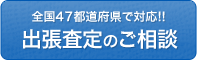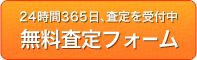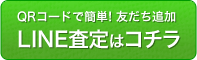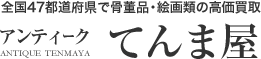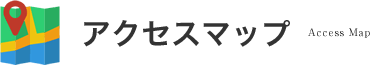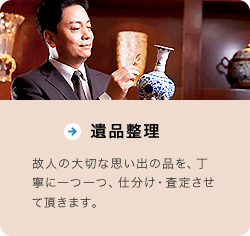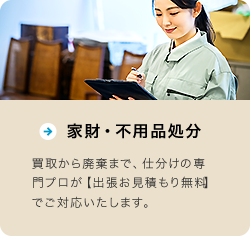作 家荒川豊蔵
荒川豊蔵(あらかわとよぞう)とは?
荒川豊蔵は、昭和を代表する岐阜県多治見市出身の陶芸家です。桃山時代の陶芸に自らの原点を見出した荒川豊蔵は、長男とともに水月窯を築きました。志野の古窯址を見つけてからの彼は、自分の理想とする陶芸を行うために、さまざまな山々に「陶土」を求めて歩き続けるようになります。そんな素材にもこだわる志野の古窯址の姿勢は、昭和の陶芸を語る上で欠かせないエピソードとなっているようです。また穴窯を築かれた後の努力も他を寄せ付けないほどのパワーがあり、その想いが作品の美しさに反映されていたとも言われています。
陶芸で知られる岐阜県多治見市に生まれた荒川豊蔵は、子供の頃からさまざまな陶磁器に触れ合いながら生活をしていました。そんな彼が陶芸家になるきっかけとなったのは31歳で、北大路魯山人との出逢いだったようです。魯山人に気に入られた荒川豊蔵は、鎌倉に築かれた星岡窯を手伝うために鎌倉に向かいます。そこで魯山人の収集した数々の陶磁器コレクションを手に取り、自分の作品に活かすようになるのです。
荒川豊蔵の陶芸家人生には、数々の失敗があります。しかし彼はそんな毎日に挫けもせず、自分が憧れる桃山時代の陶芸を目指して研究を重ねていくのです。
岐阜県加可児市には荒川豊蔵自身の作品やコレクションを集めた、「荒川豊蔵資料館」があります。ここには人間国宝ならではとも言える斬新な陶磁器がたくさん収蔵されているため、岐阜県を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。また荒川豊蔵が研究のために収集したコレクションを見れば、彼がどんな気持ちで陶磁器と向き合っていたかをイメージしやすくなります。岐阜県可児市エリアは美濃桃山陶の聖地となりますので、陶芸に興味を持っている方は、斬新な発見が多く得られると言えるでしょう。
荒川豊蔵が作った陶磁器は非常に高値で買取されることでも知られていますので、もし陶磁器を持っている場合は、アンティークてんま屋のように信頼できる買取専門店に査定依頼をしてみてください。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |