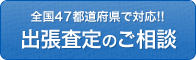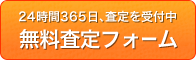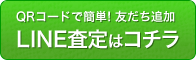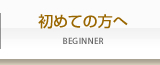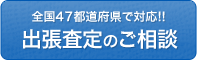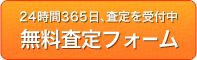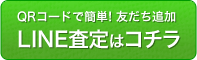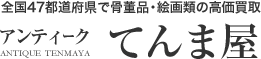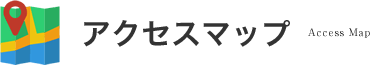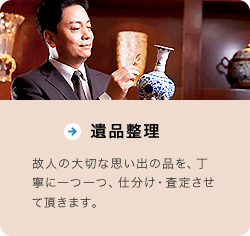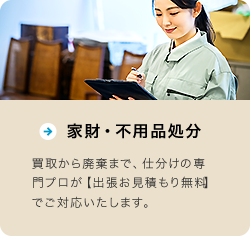作 家藤原啓
人間国宝として、日本を代表する陶芸家 藤原啓
藤原啓は1899年、岡山県の備前市に生まれました。
もともとは小説や俳句の世界に興味を抱いており、文芸誌「文学世界」に応募をした短編が第1位を獲得したことで、文学という道に従事していくことを決めました。
1919年に上京を果たし、博文館の編集部で仕事をしながら、「文学世界」の編集を努めつつ、自ら詩や俳句に没頭していきます。
地道な研究を続けることで、最終的にはフリーの作家として活動をすることになりますが、そのうちに自らの文芸作家としての才能に限界を感じるようになってしまいます。
結果として、文芸作家としての自らのキャリアに終止符を打ち、1937年故郷の備前に戻ることを決意。
故郷で知り合った正宗白鳥に師事した知人に強く勧められ、1938年より三村梅景のもとで備前焼を学びはじめます。
この段階ですでに39歳という年齢に達した藤原啓。
陶芸家としてのスタートはとても遅いものと言えるでしょう。
ところが、持ち前の努力家の気質が功を奏し、遅咲きでありながら北大路魯山人や金重陶陽など名だたる陶芸家からの薫陶を受けるチャンスに恵まれ、陶芸家として名を成すまでになりました。
骨董品マーケットで人気の藤原啓の作風とは?
数ある陶芸家の作品のなかでも、藤原啓の作品は骨董品マーケットで高く評価されています。
その理由のひとつは、彼の作品の持っている自然に備わる美しさへの礼賛。
彼は、当時の備前焼のテクニックを習得するだけでなく、備前焼が特に輝いていたと考えられる桃山時代の古い備前焼についての研究を続けていました。
桃山古備前という新しいジャンルを追及することを継続することで、藤原啓の作品は唯一無二の存在となりえたのです。
1970年には重要無形文化財保持者の認定を受け、その活動はますます盛んに。
自然の本来の力強さ、そして美しさをそのままかたちにしたような彼の作品は、いまでも根強い人気を持っているのです。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |