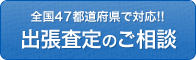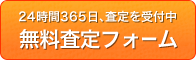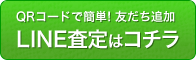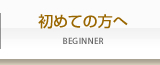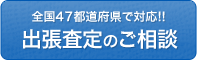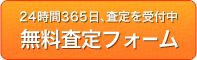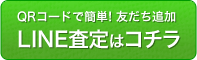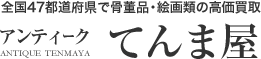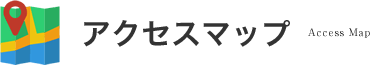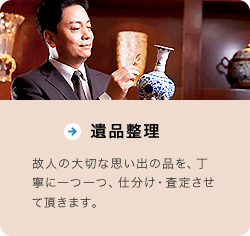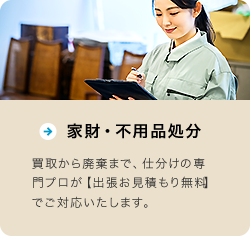作 家赤地友哉
赤地友哉(あかじゆうさい)とは?
赤地友哉は、石川県金沢市出身の「漆塗りの第一人者」と言われた人間国宝です。先祖代々続く檜物師の家庭に生まれた赤地友哉は、幼少時代から家業を継がずに漆塗りの世界に入ることを決めていました。小学校を卒業した後は、地元の塗り師・新保幸次朗に師事をして基礎を学びます。上京後は渡辺喜三郎に師事し、塗り師としての技を習得しました。1927年に独立した赤地友哉は、茶道を学びながら日本橋や京橋で使われる高級茶道具の制作に携わるようになりました。
赤地友哉の作風は「どんな作品でも基礎を大事にする」ということです。赤地友哉によって作られる曲輪手法の木地は、まさに「職人技」とも言えるレベルで狂いのない仕上がりとなります。また何度も繰り返される塗りの作業は根気強さも必要となるため、赤地友哉のプロ意識と集中力、基礎による創造だと断言できるでしょう。赤地友哉の技術は日本国内のさまざまなところで認められるようになり、1974年には重要無形文化財「髹漆」の保持者として認定されます。1980年に日本文化財漆協会会長に就任した赤地友哉は、更なる創作に励むようになります。
人間国宝である赤地友哉の作品は、全国のさまざまな美術館に収蔵されています。国立美術館には1960年~1979年に制作した12点の漆器が収蔵されており、赤地友哉の作品の中では珍しい「はりぬき朱八角中次」や「木地糸目旅棗」などがあるようです。また東京国立近代美術館にも8つの展示物があり、近代日本の漆芸を語る上で欠かせない存在になっていることが納得できる物ばかりとなっています。横浜美術館では「横浜ゆかりの作家」として赤地友哉のビデオライブラリーもあるため、彼の制作風景などが気になる人はぜひ訪れてみてください。
赤と黒という素晴らしい漆のコラボレーションが際立つ赤地友哉の作品は、古美術品として価値あるものばかりです。アンティークてんま屋では各家庭にある漆器の査定も行っていますので、気軽にお持ちください。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |