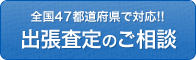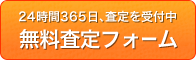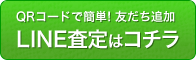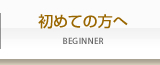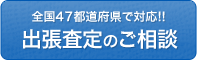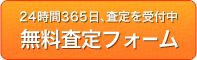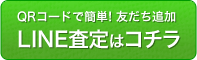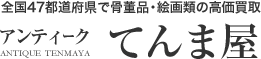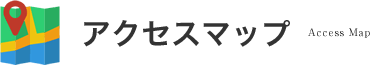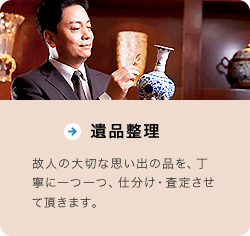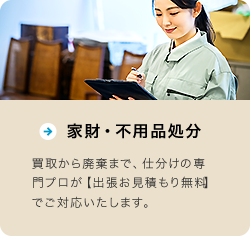作 家青木龍山
青木龍山(あおきりゅうざん)とは?
青木龍山は、佐賀県西松浦郡有田町出身の陶芸家です。一般的な有田焼は「白をベース」とした特徴がありますが、青木龍山の作品は「黒い色をした陶器」がほとんどです。本人曰く「黒が好きだから」ということですが、彼の作風は陶磁器業界の中でも異色ということで、現代でも注目され続けています。1954年に日展初入選した青木龍山は、日展の中で「天目」という地位を築きます。また1992年には陶芸家としては珍しい日本芸術院会員に就き、自身のキャリアの中で頂点を極めることができたのです。
青木龍山は、多摩美術大学の日本画家を卒業した後、高等学校の美術教師となります。約2年間の教諭としての仕事を終えた後は、祖父の興した会社に入社するという異色の経歴を持つ作家なのです。祖父の会社が倒産した後の青木龍山は、企業に属さないフリーの陶磁器デザイナーとして生計を立てるようになります。その傍ら、日展入選を目指してコツコツと努力と研究を重ね、1954年に最初の入選を果たすのです。
弟子を取ることのなかった青木龍山は、妻と共に天目を焼き続けます。そして佐賀で初めての文化勲章を受章し、多くの人の目に「漆黒の天目釉」が触れるきっかけを自ら作り上げたのです。
青木龍山が亡くなった現在では、息子の青木清高によって「青木龍山清高工房」が営まれています。この施設は青木龍山の代表作をギャラリーとして展示しながら、工房の中で新たな作品を生み出す場所となっています。サイトでは青木龍山によって語られているコラムページもあるため、工房に立ち寄る前に目を通しておいても良いでしょう。また代表作「染付家紋大皿」などの写真も掲載されていますので、予習をする感覚でチェックするのもおすすめです。
有田焼とは思えない荘厳な雰囲気が強い青木龍山の作品は、古美術品としても高値で買取される存在となっています。自宅に眠っている有田焼を含めて「価値がわからない」という場合は、気軽にアンティークてんま屋にお持ちください。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |