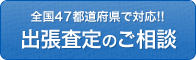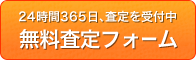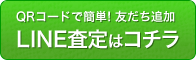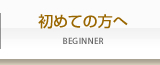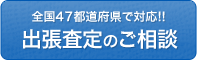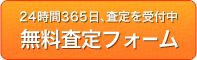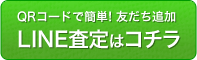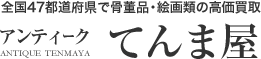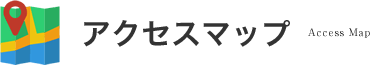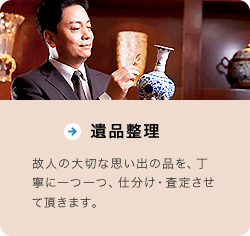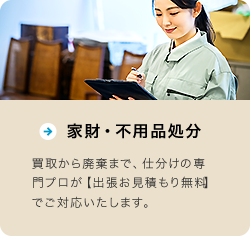作 家高橋貞次
日本を代表する刀匠 重要無形文化財保持者の高橋貞次
高橋貞次は1902年に愛媛県松山市に生まれました。
1919年、17歳のときに中央刀剣会の養成工として働くようになり、古刀のテクニックや伝統について研さんを積みました。
1936年、34歳のころには松山市に鍛錬場を開設し、1938年に開催された第1回刀剣展において内閣総理大臣賞を受賞。
その実力は多くの方の知るところとなり、1940年には由緒ある鎌倉八幡宮に御宝御神刀を鍛錬する栄誉にも預かりました。
皇室に関連したさまざまな事業を手掛け、1951年に伊勢神宮の式年遷宮が行われた際には、御宝御神刀の鍛錬を担当。
それまでの貢献や実力の高さが高く評価され、1955年に人間国宝の認定を受けました。
骨董品マーケットにおける高橋貞次の魅力とは?
高橋貞次の手による日本刀は、骨董品マーケットにおいて常に高い評価を得ています。
彼の古刀の研究の成果により、五ケ伝の奥義に精通しているその作風は、これまでに皇室に関連する御神刀の鍛錬に携わってきた実績があるように、まさに正統的なもの。
刀匠のなかで人間国宝に認定された方は、高橋貞次以外にはほとんどいないという事実が示すように、数ある日本刀のなかでも彼の手による作品がどれほど貴重なものかがおわかりいただけるのではないでしょうか。
もちろん、刀匠としては日本で初めての人間国宝認定者です。
また、彼の作り出す日本刀には、さまざまなエッセンスが取り入れられていることでも知られています。
美濃や山城、備前、大和、そして相州など、日本刀に関するいろいろな鍛錬法を会得しており、多彩な魅力を見せます。
なかでも、備前伝をもっとも得意としており、優れた作品を数多く輩出。
刀身彫刻の世界においても高く評価されており、月山流の流れを汲んださまざまな作品を作り上げています。
このように、高橋貞次の高い技術や芸術性に裏づけられた作品は、骨董品マーケットにおいてとても高い評価を得ています。
↓関連記事はコチラ
- 作 家東山魁夷の版画・リトグラフ
- 作 家版画家 加山又造
- 作 家平山郁夫の版画・絵画
- 作 家藤田嗣治(レオナール・フジタ)リトグラフ
- 作 家長谷川潔の銅版画
- 作 家片岡球子のリトグラフ
- 作 家中島千波
- 作 家村上隆
- 作 家ヒロ・ヤマガタ
- 作 家カトラン

| 店舗名 | |
|---|---|
| 買取地域 | 全国47都道府県にて買取対応 |
| TEL番号 | 0120-19-1008 |
| 所在地 | 〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-24-6 |
| 店舗受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休で営業) |
| 電話受付 | 8:00 ~ 21:00 (年中無休) |
| 定休日 | 年中無休(365日、休まず営業しています) |
| 大阪府公安委員会 | 第621096300753号 |